草山隆志医師
平成20年10月18日-平成20年11月16日
今回、米国ジュージア州マーサー大学医学部、ジュージア中央医療センターにおいてDr.Katner(Professor of Medicine/ Chief, Infectious Disease)の指導のもと、HIV/AIDSなどを含めた様々な感染症を中心に研修してきました。また研修期間中にシカゴにおいて開催されました"American colleges of the emergency physicians(ACEP)"という救急医療に関する学会に参加することができました。4週間にわたる国際医療交流・米国研修を通して、医学的な研鑽を積めただけでなく、米国全体に広がる医療問題の姿を僅かばかりとはいえ、垣間見ることができ、非常に衝撃を受けたのと同時に、どこか危機感を覚えました。その中でも二つのポイントに絞って日本の医療との相違点、今後の日本の医療体制における課題を含めて検討したいと思います。
HIV/AIDSと健康保険問題について ~No insurance, No treatment~
日本のHIV/AIDS患者数をご存知でしょうか?ちなみに2005年におけるHIV感染者数は832件、AIDS患者数は367件と報告され、合計では1199件になります。これは人口の0.001%になります。一方、アトランタ、メーコンのあるジュージア州のHIV/AIDS患者数は、2007年度の集計で35,000人にまでのぼり、アメリカ全体では100万人を超えるそうです。アメリカの人口がおよそ3億人なので約0.3%の人がHIV感染者及びAIDS患者ということになります。今回、HIV/AIDS患者の外来診療で多くの患者さんに出会いましたが、そのほとんどはAfrican Americanが占め、低教育・低収入が理由で十分な治療を受けられないでいることがありました。そして彼らの多くは感染、発病と同時に健康保険(insurance)を制限、あるいは失効されるそうです。
アメリカには日本のような公的な国民皆保健制度はなく、Medicare(65歳以上の高齢者、障害者など一部の人のみ)、Medicaid(一定の所得水準以下の低額所得者が対象)と呼ばれる公的保険に限られています。しかし、この二つを合わせても国民全体の4人に1人しか加入できないため、個人的に民間保険会社と契約する必要があります。今まではこの保険制度で支障なく医療は行われていたわけですが、この保険費が非常に高額であるために約15%の人が保険に加入できずにいます。この人達は決して貧しいというわけではなく、Medicaidの基準以上の収入はあるが民間の保険料までは払えない中間層にあたります。ご存知の通り、サプライムローン問題を皮切りに、アメリカ経済は個人だけでなく社会レベルで破綻寸前で、保険会社自体が存続が難しくなっています。連日、アメリカではニュースで大統領選の報道と同じくらいに大手保険会社への公的資金投入が報じられていました。つまり、アメリカ経済の衰退は保険会社の倒産危機へと陥り、医療自体が受けられない事態もあり得ない話ではなくなっているのです。また、米国では保険の種類により受けられる検査、治療が変わってしまいます。つまり治療方針は保険によって決まるのです。富裕層を除いて、アメリカ国民の多くは十分な医療を受けるために莫大な保険費用、医療費に頭を抱えています。多くの医療スタッフ、患者、その家族が新大統領に選出されたオバマ氏に、保険を含めた医療問題の改善を大きく期待していたのが印象的です。
十分な保険を受けられないHIV/AIDS患者は治療費を払えないために治療を開始できず、できたとしても途中で放棄することになっています。いかに医療というものが患者という個人を中心として、医療従事者のみではなく、保険、福祉、さらには経済、金融などの情勢、果ては宗教観などを含めた社会環境により支えられていることを実感しました。
それでは日本の医療現場はというと、公的皆保健制度をベースとして個人で民間の健康保険に加入している人がほとんどです。米国で見られるような保険会社による治療制限のようなことは見られません。ところが、帰国してから調べた限りでは、日本でも莫大に膨れ上がった医療費の削減を目的に、米国の保険医療を見本にして日本にも導入できないかと研究しているグループがあると知り愕然としました。確かに現状の医療費の増大を防ぐには様々な観点からのアプローチが必要で、すぐに問題を解決できる魔法のような解答はないとしても、今まさに崩壊寸前の米国保険医療を真似ようなことはナンセンスとしか思えません。
アメリカには日本のような公的な国民皆保健制度はなく、Medicare(65歳以上の高齢者、障害者など一部の人のみ)、Medicaid(一定の所得水準以下の低額所得者が対象)と呼ばれる公的保険に限られています。しかし、この二つを合わせても国民全体の4人に1人しか加入できないため、個人的に民間保険会社と契約する必要があります。今まではこの保険制度で支障なく医療は行われていたわけですが、この保険費が非常に高額であるために約15%の人が保険に加入できずにいます。この人達は決して貧しいというわけではなく、Medicaidの基準以上の収入はあるが民間の保険料までは払えない中間層にあたります。ご存知の通り、サプライムローン問題を皮切りに、アメリカ経済は個人だけでなく社会レベルで破綻寸前で、保険会社自体が存続が難しくなっています。連日、アメリカではニュースで大統領選の報道と同じくらいに大手保険会社への公的資金投入が報じられていました。つまり、アメリカ経済の衰退は保険会社の倒産危機へと陥り、医療自体が受けられない事態もあり得ない話ではなくなっているのです。また、米国では保険の種類により受けられる検査、治療が変わってしまいます。つまり治療方針は保険によって決まるのです。富裕層を除いて、アメリカ国民の多くは十分な医療を受けるために莫大な保険費用、医療費に頭を抱えています。多くの医療スタッフ、患者、その家族が新大統領に選出されたオバマ氏に、保険を含めた医療問題の改善を大きく期待していたのが印象的です。
十分な保険を受けられないHIV/AIDS患者は治療費を払えないために治療を開始できず、できたとしても途中で放棄することになっています。いかに医療というものが患者という個人を中心として、医療従事者のみではなく、保険、福祉、さらには経済、金融などの情勢、果ては宗教観などを含めた社会環境により支えられていることを実感しました。
それでは日本の医療現場はというと、公的皆保健制度をベースとして個人で民間の健康保険に加入している人がほとんどです。米国で見られるような保険会社による治療制限のようなことは見られません。ところが、帰国してから調べた限りでは、日本でも莫大に膨れ上がった医療費の削減を目的に、米国の保険医療を見本にして日本にも導入できないかと研究しているグループがあると知り愕然としました。確かに現状の医療費の増大を防ぐには様々な観点からのアプローチが必要で、すぐに問題を解決できる魔法のような解答はないとしても、今まさに崩壊寸前の米国保険医療を真似ようなことはナンセンスとしか思えません。
救急医療について ~北米型ER~
従来の日本における救急医療体制は、都道府県の作成する医療計画に基づき二次医療圏までを範囲として、救命救急センターを主体とした3次救急医療で対応しています。それぞれの病院が重症度に応じて患者の受け入れ態勢をとっている所が多いと思います。近年、救急搬送患者の受入れ拒否やたらい回し、救急外来のコンビニ化など多くの問題を抱えるようになり、ER型救急医療が注目されるようになりました。これは北米型救急医療モデルのことを指し、①重症度、傷病の種類、年齢によらず全ての救急患者をERで治療する、②救急医がすべての救急患者を診療する、③救急医がERの管理運営を行う、④研修医が救急診療する場合には、ERに常駐する救急専従医が指導を行う、⑤救急医はERでの診療のみを行い、入院診療を担当しないなどの特徴が挙げられます。このことはテレビや新聞の報道、ドラマなどで取り上げられていることもあり、すでに一般的になっているかもしれません。確かにその特徴を見ると、いつでも最善の医療が受けられる、非常に便利な外来のように見えます。それでは現在の米国救急体制には問題点はないのでしょうか。そして日本で同様な救急体制を確立できれば、現在の問題を解決、改善できるのでしょうか?
アメリカで実際の救急外来現場を見てみると、そこには非常に多くのナース、EMS(救急隊員)が最前線で患者を診ているのに驚きました。その人数はナースのみで30名を超えており、さらには心電図専門の技師、ギプスを巻く専門の技師、人工呼吸専門の技師など、作業の細分化が非常に目立ちました。合計するとかなりの数のスタッフで救急外来が成り立っています。しかし思ったよりも医師の数は少なく、50弱のベッドに対して2名のみであとはレジデントと数名の学生が診ていました。彼らはあくまでもスタッフを適切にコントロールするのみで自分の仕事の範囲以外のことはまったく関与しません。驚くべきことに心電図をとられるのを待って1~2時間もベッド上で放置されている患者を何人も見ました。医師、ナースは心電図を読めても、必要がないから検査することはできないそうです。
ACEPの会場でアメリカの病院のERでレジデントの3年目として勤務しておられる日本人の先生に話を伺うことができ、とても印象的な会話がありました。 「アメリカで実際に働いているなんてすごいですね。」 「何もすごくないよ。僕ができるのはアメリカでのER。日本に帰って日本の救急で対応できるか心配だ。」
今回渡米し研修するまで、どこか心の中でアメリカの医療は日本より進んでいて、何か"すごい"はずと思っていました。しかし、そこにはあまりにも日本とかけ離れた現実があり、すごいと思うよりも、その違いに戸惑う毎日でした。医療体制、保険問題だけでなく、文化や環境そのものに対してだったのかもしれません。アメリカを知ることで日本は"異なる"ということを強く実感できました。それは日本の医療が特別という意味ではありません。日本は日本、黒部は黒部なのだということを再認識したのです。
私は今回の研修を通してアメリカとの多くの"違い"を体験し、自分自身の、そして黒部、日本の医療を考えるいい機会になりました。私たちを取り巻く医療の問題を解決する魔法のような答えはすぐにはないかもしれません。しかし、微力ながら私にできることといえば、少なくとも目の前の患者を助けるという点で、日本もアメリカもなんら違いはないのですから、日々精進して研鑽を積んでいきたいと思います。
ACEPの会場でアメリカの病院のERでレジデントの3年目として勤務しておられる日本人の先生に話を伺うことができ、とても印象的な会話がありました。 「アメリカで実際に働いているなんてすごいですね。」 「何もすごくないよ。僕ができるのはアメリカでのER。日本に帰って日本の救急で対応できるか心配だ。」
今回渡米し研修するまで、どこか心の中でアメリカの医療は日本より進んでいて、何か"すごい"はずと思っていました。しかし、そこにはあまりにも日本とかけ離れた現実があり、すごいと思うよりも、その違いに戸惑う毎日でした。医療体制、保険問題だけでなく、文化や環境そのものに対してだったのかもしれません。アメリカを知ることで日本は"異なる"ということを強く実感できました。それは日本の医療が特別という意味ではありません。日本は日本、黒部は黒部なのだということを再認識したのです。
私は今回の研修を通してアメリカとの多くの"違い"を体験し、自分自身の、そして黒部、日本の医療を考えるいい機会になりました。私たちを取り巻く医療の問題を解決する魔法のような答えはすぐにはないかもしれません。しかし、微力ながら私にできることといえば、少なくとも目の前の患者を助けるという点で、日本もアメリカもなんら違いはないのですから、日々精進して研鑽を積んでいきたいと思います。

Kennedy Space Center

Kennedy Space Center
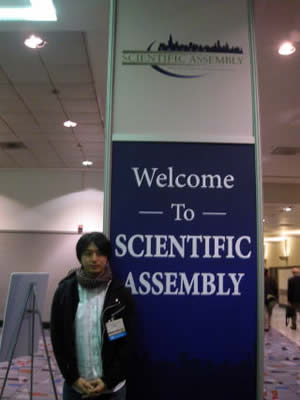
ACEP in Chicago

